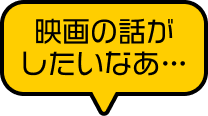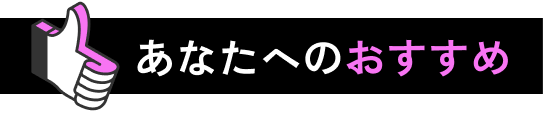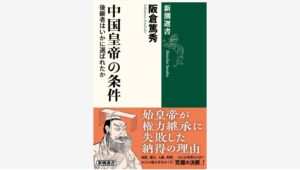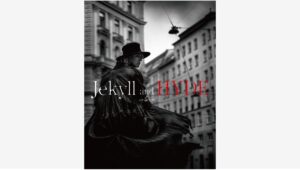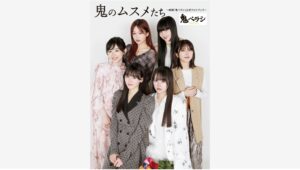【Amazon調査隊】新潮社が問うエリート外交官の戦争責任
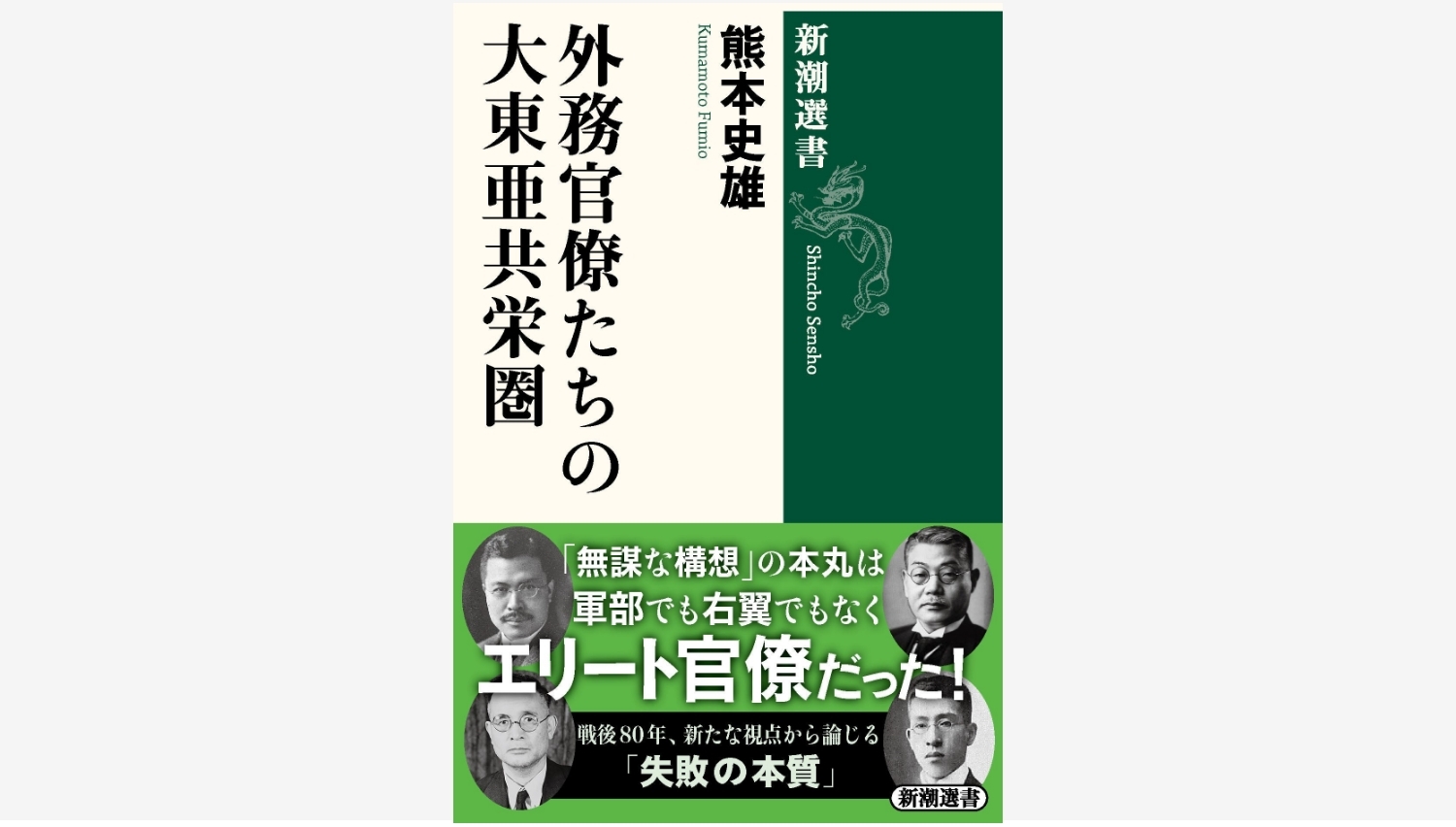
戦後80年、新たな視点からエリート外交官たちの戦争責任を問う
《エリート外交官が大東亜共栄圏構想を積極的に推進した張本人であったことを明らかにする『外務官僚たちの大東亜共栄圏』(熊本史雄著、新潮選書)が、新潮社から5月21日(水)に発売されます。
駒沢大学教授の熊本史雄さんは、かつて外務省外交史料館の事務官を務めていた経験を持つ、近現代史のエキスパートです。その熊本さんが、「陸軍が暴走し、外務省もそれに引きずられて、日本は大東亜戦争に突入した」というこれまでの通説的理解に異議を唱え、むしろエリート外交官たちが大東亜共栄圏構想を積極的に推進した張本人であったことを、史料に基づいて明らかにするのが本書です。日露戦争時の外相・小村寿太郎をはじめ、幣原喜重郎、重光葵、有田八郎、松岡洋右など外務省の面々が、紆余曲折を経ながらも外交思想として大東亜共栄圏構想を練り上げていく経緯を、臨場感あふれる筆致で描いています。戦後80年、外交が官邸主導となり、ともすれば外務省が「官邸にひきずられた」ようにも見える昨今、あらためて外交官たちの主体性を問い直す際に参考になる一冊です。》
引用元: PR TIMES
最近、歴史に関する本を読むと、まるでタイムマシンに乗って過去を旅しているような気分になります。特に、知らなかった事実が明らかになると、まるで新しい世界が開けたような感覚に陥ります。皆さんもそんな経験、ありませんか?
エリート外交官たちの新たな視点
新潮社から発売された『外務官僚たちの大東亜共栄圏』は、戦後80年を迎えた今、エリート外交官たちの戦争責任を新たな視点から問い直す一冊です。著者の熊本史雄さんは、外務省外交史料館での経験を活かし、これまでの通説に異議を唱えています。彼によれば、陸軍の暴走に引きずられたのではなく、むしろ外交官たちが積極的に大東亜共栄圏構想を推進したというのです。
外交官たちの主体性を問う
本書では、日露戦争時の外相・小村寿太郎をはじめ、幣原喜重郎、重光葵、有田八郎、松岡洋右といった外務省の面々が、どのようにして大東亜共栄圏構想を練り上げていったのかが描かれています。外交が官邸主導となりがちな現代において、外務省の役割や外交官たちの主体性を再考する際に、非常に参考になる内容です。
歴史の教訓を未来へ
戦後80年を経た今、過去の外交政策やその背景を理解することは、未来の外交を考える上で重要です。『外務官僚たちの大東亜共栄圏』は、過去の失敗から学び、未来に活かすための貴重な教訓を提供してくれるでしょう。歴史に興味がある方はもちろん、現代の外交に関心がある方にもぜひ手に取っていただきたい一冊です。
※ 本記事は、2025年5月21日のPR TIMESの記事を引用しております。キャンペーンの期間及び内容は、予告なく変更・終了する場合があります。予めご了承ください。